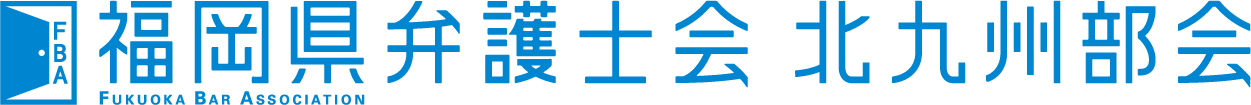相続法改正③(相続人以外の親族の貢献を考慮する制度の新設)
1 はじめに
相続法(民法の一部)が改正されて「特別の寄与」という制度(民法1050条)が新設されました。この制度は令和元年7月1日以降に亡くなられた方の相続手続に適用されます。
もともと,亡くなられた方(故人・被相続人)に対して経済的に貢献をしていた相続人には,その貢献分(経済的価値)を被相続人が遺した財産(遺産)の中から「寄与分」として切り分け,貢献した相続人に取得させるという制度がありましたが,この「寄与分」制度は相続人の資格を有する人にしか認められていませんでした。
相続人以外の親族の中にも,故人の生前に生活や事業を支援するなどして,故人の財産増加に貢献された方が一定程度いますが,そのような親族が「相続人ではないとの理由で遺産の中から何も取得できないのは不公平である」との指摘が以前からありました。この不公平感を解消するために新設されたのが,今回の「特別の寄与」という制度です。
2 どのような場合に「特別の寄与」を主張できますか?
「特別の寄与」を主張できるのは,次の場合です。
(1) 故人(被相続人)の親族であること
(2) 被相続人に対して生前に無償で労務を提供したこと
(3) その結果,被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと
以下,上記の(1)から(3)の条件を個別にご説明します。
(1) 被相続人の親族であること
「特別の寄与」の主張ができるのは相続人以外の故人の親族に限られ,親族とは「6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族」とされています。例えば,男性の方が亡くなり,その方に妻と息子1人がいた場合,妻と息子1人が故人の相続人となりますが,相続人ではない息子の妻(故人の義理の娘で1親等の姻族にあたります)や故人の妹(2親等の血族にあたります)も,故人の生前に日常生活の世話をするなどしていた場合には「特別の寄与」が認められる可能性のある親族にあたります。
ただし,内縁関係や同性婚の配偶者については,法律上の「親族」に当たらないため,「特別の寄与」を主張できません。
(2) 被相続人に対して生前に無償で労務を提供したこと
①「無償」とは,どのような場合でしょうか?
「特別の寄与」の主張ができるのは,相続人以外の親族が,故人(被相続人)に対して,生前に「無償」で労務を提供していた場合に限られますが,「無償」か否か(つまり「ただ」で貢献したかどうか)は,故人と「特別の寄与」を主張したいと考えている親族との関係や,故人や相続人を含む関係者の認識などを総合的に考慮して判断されます。
例えば,上記の事例で,故人の息子の妻が,故人(義父)の身の回りの世話をしていた一方で,義父から生活費を貰っていたという場合にも,息子の妻(義理の娘)による義父に対する介護の内容と義父から受領した生活費の金額を比較したり,生前の義父と義理の娘との関係性なども考慮して「無償」と評価できるか否かが判断されますので,一概に「特別の寄与」を主張したい親族が故人から生前に生活費を貰っていたからと言って「無償ではない」と判断されるものではありません。
②「労務の提供」とは,何でしょうか?
一般的には,①故人の家業を手伝っていた場合(家業従事型)や,②親族として当然の程度を超えて故人の身の回りの世話をしていた場合(療養看護型)が「労務の提供」に該当するとされていますが,それ以外でも「特別の寄与」が認められる場合があります。
(3) 被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと
相続人以外の親族が故人(被相続人)に対して生前に労務を提供したことによって,故人(被相続人)の財産の維持または増加に特別の寄与をした(遺産の形成に特別の貢献があった)と認められることが必要です。
3 「特別の寄与」の主張の仕方は?
(1) 相続人に対して「特別寄与料」を請求して「協議」します
故人に対する生前の特別な貢献を金銭的に評価した「特別寄与料」を故人の相続人に対して請求をすることができます。相続人全員に請求しても良いし,特定の相続人にだけ請求することもできます。
ただし,特定の相続人にだけ請求する場合には,請求可能な金額は「特別寄与料の額に各相続人の法定相続分(または遺言書で指定された相続分)を乗じた金額」に留まります。例えば,上記の事例(義理の娘が義父の世話をしていた事案で遺言書がなかった場合)で義理の娘が義母だけに特別寄与料を請求する場合には,請求可能な金額は「特別寄与料の総額に義母の法定相続分(2分の1)を掛けた金額」に留まりますので,特別寄与料を全額請求したい場合には,相続人全員に請求をする必要があります。
(2) 相続人との「協議」がまとまらない場合は?
家庭裁判所に対して,特別の寄与に関する処分の「調停」又は「審判」を申立てることができます。
なお,「調停」は家庭裁判所(調停員)が介在した話し合いによって解決する手続であり,「審判」は家庭裁判所(審判官)による後見的な判断によって解決する手続ですので,調停を経ないで「審判」を申し立てた場合にも,話し合いでの円満な解決を期待した家庭裁判所の判断で「調停」に付される可能性があります。
調停等は相続人(請求の相手方)の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所で行われます。調停等の申立てに必要な費用や書類などについては,裁判所のホームページを参考にしてください。
4 特別寄与料は,どのように決まりますか?
(1) 特別寄与料の算定には「一切の事情」が考慮されます
特別寄与料の金額は「一切の事情」を考慮して定めるとされています(民法1050条3項)が,この「一切の事情」には親族(特別寄与者)による寄与(貢献)の程度・時期・方法や故人が遺した財産(遺産)の金額などが含まれます。
具体的な金額については,一概には言えませんが,これまでの相続人における「寄与分」制度の事案が参考になりますので,特別寄与料の請求をご検討の方は弁護士などの法律の専門家にご相談ください。
(2)【注意点①】故人が「遺贈」をしていた場合
特別寄与料の金額は,故人(被相続人)が死亡(相続開始)時に有していた財産額から遺贈額を差し引いた残額を超えることができません(民法1050条4項)。
「遺贈」とは故人が生前に遺言書で自分の財産を死後に誰かに贈与することを言いますが,上記の事例(義理の娘が義父の世話をしていた事案)でご説明をします。
義父(被相続人)の死亡時の財産が3000万円あった一方,義父が生前に「A銀行の預金1000万円を息子に譲る」との遺言書を作成していたとします。この遺言は特定の財産を贈与する内容のもので法律的には「特定遺贈」と評価されます。この場合,特別寄与料は死亡時の財産額から遺贈額を除いた残額を超えることができないため,義理の娘が特別寄与料として義母や夫(故人の息子)に請求できる金額は,義父の死亡時の財産3000万円から息子への遺贈額1000万円を差し引いた2000万円が上限となります。
なお,「遺贈」には上記の「特定遺贈」以外にも「包括遺贈」があり,「包括遺贈」とは遺贈する財産を特定せずに財産に対する割合(例えば,遺産の2分の1)を指定して遺贈する方法ですが,この「包括遺贈」は相続時の財産から控除する対象には含まれません。上記の事例で,義父が「私の財産の2分の1を息子に譲る」という内容の遺言書を作成していた場合には,義理の娘が主張できる特別寄与料の上限は3000万円となります。
(3)【注意点②】請求には「期間制限」があります!
特別寄与料の請求にあたり,家庭裁判所に対して「特別の寄与に関する処分」の調停又は審判を申立てる場合には「期間制限」があり,①特別寄与者が相続の開始(故人の死亡)及び相続人を知った時から6か月を経過したとき,又は②相続開始の時から1年を経過したときは,申立てることができません(民法1050条2項ただし書)。
5 特別寄与料の請求をお考えの場合には,弁護士に一度ご相談を!
これまでお話しした以外にも,相続人が故人から生前に特別の経済的な利益(特別受益)を受けていた場合など,特別寄与料の請求には相続に関する様々な法的な問題が絡みますので,特別寄与料の請求をお考えの方は弁護士会の法律相談センターでご相談ください。